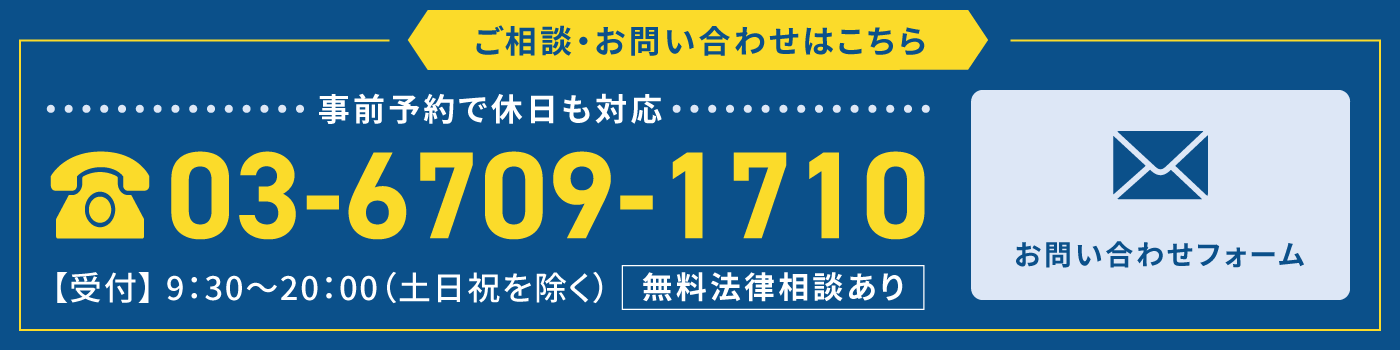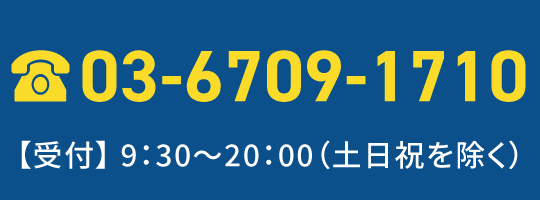このページでは,脊髄損傷について紹介しています。
脊髄損傷と診断された場合,後遺障害として認定されるのかについてご説明します。
なお,本ページに記載された医学的な説明は分かりやすさを重視していることに留意ください。
このページの目次
脊髄損傷とは
脊髄とは,脳と連続した器官であり,脳から下に向かって伸びた円柱状の神経組織の器官です。
上から,頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄となっています。
脊髄は中枢神経であり,中枢神経が阻害されると,阻害された場所に応じた麻痺が生じます。
例えば,頸髄損傷は四肢麻痺(両手腕および両足),腰髄損傷は両下肢の麻痺というようになっています。
また,感覚障害としての痺れや痛みについても,阻害された場所に応じて痺れや麻痺が生じます。
このように,阻害された場所に応じて,麻痺や痛み・痺れが生じるため,阻害された場所とは異なる場所に麻痺や痛み・痺れが生じた場合は,医学的な所見と矛盾していると判断されることになります。
脊髄損傷の後遺障害等級について
脊髄損傷では,以下のとおりの後遺障害等級に該当する可能性があります。
- 第1級(生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの)
- 第2級(生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの)
- 第3級(生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの)
- 第5級(極めて軽易な労務にしか服することができないもの)
- 第7級(軽易な労務にしか服することができないもの)
- 第9級(通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの)
- 第12級(通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの)
具体的には,どのような要件があれば各等級に認定されるかは割愛しますが,いずれも麻痺の範囲および程度が重要となります。
脊髄損傷が後遺障害として認定されるためには
脊髄損傷が後遺障害として認定されるためには,
- そもそも脊髄損傷を生じさせるような事故状況であったか
- 事故直後に脊髄損傷が発症しているか
- 画像所見があるか
- 画像所見と整合する症状が生じているか
- 症状経過は矛盾しないか
などが問題になります。
例えば,①では,軽微な衝突事故の場合,そもそも脊髄損傷まで生じないのではないかと判断されてしまうおそれがあります。
したがって,後遺障害等級認定の申請をする際には,事故状況を詳細に説明するとともに,場合によっては意見書も作成することが望ましいといえます。
事故との因果関係について
次に,事故によって脊髄損傷が生じたとしても,事故前から存在していた症状であるとして因果関係が否定されるおそれもあります。
このような場合,前記②のように事故直後に脊髄損傷が発症している場合,他でもなく当該事故によって脊髄損傷が発症と言いやすくなります。
したがって,事故との因果関係も争いになることがあります。
素因減額について
最後に,事故によって脊髄損傷が生じたと認められ,後遺障害等級が認定された場合でも,素因減額という問題があります。
これは,事故前から存在していた既往症の影響が大きい場合,賠償額が一定程度減額されるというものです。
このような場合,事故前から存在していた既往症がどの程度なのか(例えば,「病気」といえるほどのものなのか,単なる経年劣化に過ぎないのか),既往症が存在していたとしても事故による負傷部位とどの程度合致しているのかなどを検討することになります。
素因減額については,医学的判断を要するものの,最終的には法的判断ですから,今までに蓄積された裁判所の判断を詳細に検討する必要があります。
早期の相談を!
脊髄損傷は,全身麻痺なども想定される重大な後遺障害となりかねません。
後遺障害として認定されるためにも,まずは後遺障害の申請をされる前にご相談することをおすすめします。
脊髄損傷に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。